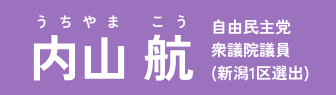【教育を考える夜】
昨日は私立幼稚園・認定こども園協会の総会&懇親会へ。
子どもの数は今の二十歳が生まれた時と比べると60%くらいになっていて、私立大学の連携が始まっていることは過去の投稿で書きました。
その影響をもろに受けているのが幼稚園保育園こども園の皆さんなわけで、施設の再編(新潟市立の)や新たな補助について様々な議論をしましたが、専門的なのでちょっと割愛。
一方で子どもたちの教育がいかにあるべきか、という議論もぜひ皆さんとしていきたいです、という挨拶をさせていただき、まあ、そんな議論する時間もないだろうなと思っていましたが、ある委員の方が「障がい(おそらく発達障害も含んでいると思われます)を持っているこどもで、どうしても園を辞めてもらわなければならない場合について、という意見が出され、ちょっと総会は延長戦へ。
結局、いろんな意見が出ましたが、別日にこういう意見交換をする場を作ろうということで私にお役目が回ってきましたので、またこういう議論をしたいなと思います。
日本では障がい者用の学級が用意されていて、国連から辞めろと言われているわけですが、いろんな障がいを持つ子どもたちと「いわゆる」普通の子どもたちが一緒になれば、まあ授業崩壊するだろうな、というのは私の頭が凝り固まっているからでしょうか。
おそらくインクルーシブ教育とかウェルビーイングとか探求学習とか、そういう所から見ると、障がいがあるこどもたちと一緒に学んで学級が崩壊するような授業は所詮「詰め込み教育」ですよね、と、そんな風に見えるのかな。
確かに個別最適化された学びの場が用意され、障がいがある子もない子も共に学び、ある時は独自に興味があることに集中し、社会の縮図みたいな学校が出来上がれば、最高だとは思います。
単純な科目の授業は東京の偉い先生のめちゃくちゃわかりやすい偏差値50を対象にしたビデオ授業にして、それについていけない人を補助するくらいの対応で済ませると。
物足りない人は偏差値60の授業とかいろいろ分けていて、それ見てやってくれと。
で、探求学習とか生き抜く力とかそういうことを先生には集中してやってもらおう、とか。
それをする先生へのカリキュラムはいろいろいじる必要がありますし、そもそも保護者がそんな教育を望んでいない方が多いと思いますし(偏差値大事と思っている人が多いですし、別に私も我が子のことになれば偏差値無視しません。)、そもそも日本の教育は抜本的「革命」が必要に迫られるほどひどすぎるものとも思ってませんし(改革は常に必要ですが)、その結果生まれた日本が世界と比べてダメになっているとは全く思ってません。
ただ、私はどっちかというとみんな一緒に学んだ方がいいなと思う派です。
集団の中で自分だけが良くなればいいという発想は持続可能じゃない。
個人主義と集団主義の両方の良さについては以前書きましたので割愛。
働き方改革で、働く時間が制限され、能力の高い人が勝ちやすい社会です。
で、そこからこぼれた人を税金を使って助ける、という方向にどんどん進んでいませんか?と、ちょっと思っていて。
政治は税の再配分の機能を持っていますから、それは大事ですが、振り子が振れすぎるとお金なくなりますよねと。
幼稚園小学校のうちからいろんな人がいて、助け合って社会が成り立っているということを良く知る必要があるのではないかと。
いろんな障がいを抱えながら(というかその特性を生かして)、そういう皆さんが、世界の節目で革命的なことをやってきたことも事実。
この時代を「生き抜く力」は大事ですが、これからは「ともに生き抜く力」ですね。
お互いが手を取り合って力強く「ともに生き抜く社会」を作っていけたらいいなと思って、今考えていることを無造作に書いてみました。
無造作なので意見まとまってません。
これから皆さんと一緒に考えたいと思います。
なんか教育について考えるとかいうと、戦後教育がどうとかまた戦前の集団主義がとか教科書問題がとか、そういう議論と勘違いされがちで、結構本質的な議論がなされていないような気もするので、いろんな方といろんな話をしていきたいなと思います。
あ、写真を撮り忘れたので、我が家の過去の写真を適当に貼ります。
本日はここまで。
それでは本日もよろしくお願い致します!!
今日もきっと、いいことがある。